朝、仕事に行くときの道中で。
霜の降りる、冷え込んだ朝でした。
自宅の車のフロントウィンドウに、ペットボトルで水をかけている人がいました。
霜取りをしているのですね。
反射的にぎょっとしましたが。
ワタシが免許を取ったのは学生時代、信州でのことです。
かの地では、水などかけたらたちどころに凍るわけで、やってはいけないことの初歩の初歩。
だから、ぎょっとしたのです。
千葉県は、温かいのだな。
ええと。
このブログでは珍しく、発売間もない製品です。
![]()
乗ったことはおろか、見たことすらない京阪特急。
1輌は旧形式からの編入で、台車も違って、両運転台時代の面影を残していて、というマニアックな編成です。
3輌編成だから、深夜帯の特急列車か。
外箱の解説によれば、1970(昭和45)年ごろの最盛期をプロトタイプとしたとか。
画像左側の1905号車が片運転台化されたのが1967(昭和42)年で、
1970年にはヘッドライトが2灯化されたそうですから、その間の姿ということになります。
![]()
鳩のマークの特急ヘッドサインは、添付シールを貼ることになっています。
無いと、ちょっと間が抜けていますね。
いろいろ調べまして、どうやら仕切板はベージュっぽいことはわかりました。
近そうな色として、国鉄特急色の「クリーム4」号を筆塗り。
![]()
枕カバーも、筆塗りです。
寸法を均一にするならシールを貼るのも一案ですが、ワタシは経年によりはがれるのが嫌なので、筆塗り。
ちょっとのばらつきは、気にしないことにしています。
ところで、座席の色はもっと赤っぽいと思っていたのですが、違うのでしょうね。
床の色は、何色だろう?
仕切板を塗ったら、運転台越しに奥行きが出たような気がします。
この画像だと、わからないか。
![]()
そのうち、ジャンパ線も付け足そう。
側窓越しに、枕カバーの白色がいいアクセントになってくれました。
実車には窓保護棒がありましたが、この製品では省略されています。
10年以上前に、「じゃまな保護棒などありません、窓いっぱいの風を浴びて…」と締めくくった工作記事がありました。
ワタシも無いままにしておこう、模型なのですから。
![]()
予算の都合で、動力などの組み込みは当面見送りですよ。
霜の降りる、冷え込んだ朝でした。
自宅の車のフロントウィンドウに、ペットボトルで水をかけている人がいました。
霜取りをしているのですね。
反射的にぎょっとしましたが。
ワタシが免許を取ったのは学生時代、信州でのことです。
かの地では、水などかけたらたちどころに凍るわけで、やってはいけないことの初歩の初歩。
だから、ぎょっとしたのです。
千葉県は、温かいのだな。
ええと。
このブログでは珍しく、発売間もない製品です。

乗ったことはおろか、見たことすらない京阪特急。
1輌は旧形式からの編入で、台車も違って、両運転台時代の面影を残していて、というマニアックな編成です。
3輌編成だから、深夜帯の特急列車か。
外箱の解説によれば、1970(昭和45)年ごろの最盛期をプロトタイプとしたとか。
画像左側の1905号車が片運転台化されたのが1967(昭和42)年で、
1970年にはヘッドライトが2灯化されたそうですから、その間の姿ということになります。

鳩のマークの特急ヘッドサインは、添付シールを貼ることになっています。
無いと、ちょっと間が抜けていますね。
いろいろ調べまして、どうやら仕切板はベージュっぽいことはわかりました。
近そうな色として、国鉄特急色の「クリーム4」号を筆塗り。
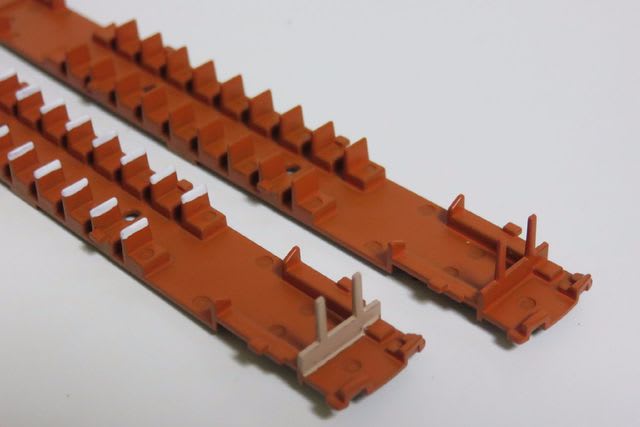
枕カバーも、筆塗りです。
寸法を均一にするならシールを貼るのも一案ですが、ワタシは経年によりはがれるのが嫌なので、筆塗り。
ちょっとのばらつきは、気にしないことにしています。
ところで、座席の色はもっと赤っぽいと思っていたのですが、違うのでしょうね。
床の色は、何色だろう?
仕切板を塗ったら、運転台越しに奥行きが出たような気がします。
この画像だと、わからないか。

そのうち、ジャンパ線も付け足そう。
側窓越しに、枕カバーの白色がいいアクセントになってくれました。
実車には窓保護棒がありましたが、この製品では省略されています。
10年以上前に、「じゃまな保護棒などありません、窓いっぱいの風を浴びて…」と締めくくった工作記事がありました。
ワタシも無いままにしておこう、模型なのですから。

予算の都合で、動力などの組み込みは当面見送りですよ。